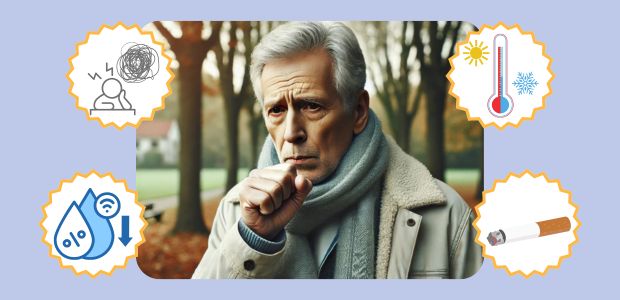いつもと違う変な咳が出る!考えられる病気や対処法は?

咳は、ウイルスや細菌、ホコリなどの異物を体外に排出するための防御反応としての役割を持っています。健康な人でも咳をすることはあり、必ずしも悪いものとは限りません。
しかし、「普段と違う音がする」「急に激しく咳き込んで止まらない」など、いつもと異なる咳が出る場合は、何らかの病気が潜んでいる可能性があるため注意が必要です。
この記事では、変な咳の原因となる病気やその対処法についてくわしく解説します。
目次
1.変な咳とは
普段とは違う音の咳が出たり、特に理由もなく突然咳き込むことがあると、風邪ではない別の病気ではないかと心配になるかもしれません。
この章では、「いつもと違う」「何か変」と感じる咳を紹介します。
1-1.変な音がする
呼吸器感染症や慢性的な炎症で、空気の通り道である気道が狭くなると、その影響で以下のような音の咳が出ることがあります。
・「ケンケン」という犬の鳴き声のような咳が出る
・オットセイが吠える声のような咳が出る
・咳とともに「ヒューヒュー」「ゼイゼイ」という呼吸音が聞こえる
・咳をした後に「ヒュー」という笛を吹いたような音が出る
感染症が原因なら、経過を見ているうちに咳が自然に改善することもありますが、呼吸が苦しくてつらいようなら、病院を受診した方がよいでしょう。
1-2.突然咳が出て止まらない
タバコの煙や冷たい空気を吸ったときなど、何らかのきっかけで咳が出て止まらなくなる人がいます。
健康な人でも、誤飲などが原因でむせて咳き込むことはありますが、突然咳き込むことが多いようなら、何らかの病気が原因かもしれません。
1-3.特定の条件で咳が出る
以下のように、特定の時間やタイミングで咳が出る人がいます。
・夜間から早朝にかけて
・季節の変わり目
・食後
咳が特定の条件で頻繁に起こる場合は、その原因を突き止め、適切な治療や予防策を講じることが重要です。
1-4.体調は悪くないのに咳が出る
鼻水や熱などの症状がないにもかかわらず咳が出たり、風邪などの呼吸器感染症にかかった後、体調が良くなったにもかかわらず咳だけが続くことがあります。
通常、風邪をひいて咳が出ても、鼻水や熱などの他の症状と同じく、1週間程度で治まって、体調も回復することがほとんどです。
しかし、体調が回復したと感じるのに咳が続くのであれば、風邪とは別の病気が関係している可能性があります。
1-5. 咳とともに血痰が出る
咳とともに血の混じった痰が出る場合、呼吸器からの出血が疑われます。
誤って、鼻の中や口の中の傷からの出血や、歯周病などによる歯ぐきからの出血を、血痰と混同しているケースもありますが、咳とともに血痰が出ることが続くようなら、肺に異常が生じている可能性があります。
2.変な音の咳が出る病気
咳の音には、大きく分けて「コンコン」という乾いた音(乾性咳嗽)と、「ゴホゴホ」という湿った音(湿性咳嗽)があります。
ただし、病気や症状によっては、普段あまり耳にしない特徴的な音の咳が出ることもあります。
2-1.クループ症候群
クループ症候群は、喉の奥にある咽頭付近が炎症で腫れ、気道が狭くなることで起こる症状です。主な原因はウイルス感染ですが、細菌感染やアレルギーによる場合もあります。
初めは咳や鼻水、発熱などの症状が出ますが、進行すると喉の奥がさらに狭くなり、「ケンケン」という犬の鳴き声のような咳や、「オウッオウッ」というオットセイの鳴き声のような変わった音の咳が出ます。
この症状は、特に免疫力が弱く、喉の奥が狭くなりやすい生後6か月から3歳までの乳幼児に多く見られます。
2-2.喘息
空気の通り道である気道に慢性的な炎症が生じることで、咳や息苦しさなどの症状が現れる病気です。
喘息の人が呼吸をすると、「ヒューヒュー」「ゼイゼイ」という特徴のある音がすることがあります。この呼吸音を「喘鳴(ぜんめい)」といいます。
喘息の咳は、市販の咳止め薬では治まりません。治療には、吸入ステロイド薬や気管支拡張薬などの処方薬が必要です。
2-3.百日咳
百日咳菌に感染して発症する感染症です。最初は軽い咳から始まり、次第に強い咳へと悪化していきます。
この病気の咳の特徴は、連続して「コンコン」と激しく咳き込んだ後に、息を吸う際の「ヒュー」という音が出ることです。
咳は徐々に治まってきますが、完全に出なくなるまでには100日ほどかかります。
3.突然咳が出て止まらなくなる病気
何らかのきっかけで咳が出て止まらなくなる人は、呼吸器の病気のほか、アレルギーが関与している場合があります。
3-1.アレルギー
花粉やペットの毛など、特定の物質を吸い込んだり触れたときに咳が出るなら、花粉症や猫アレルギーなどのアレルギーが原因だと考えられます。特定の食材を口にしたときに咳が出る時は、食物アレルギーを疑います。
また、アレルギー性鼻炎によって鼻水が喉に垂れ込むと、鼻水によって喉が刺激され、咳が出ることがあります。
アレルギーの有無や、アレルギーを引き起こす物質(アレルゲン)の種類は、血液検査で調べることができます。
原因となる物質がわかったら、その物質を避けて生活したり、抗アレルギー薬などを服用して症状を緩和します。
3-2.喘息、咳喘息
喘息や咳喘息の人は、「冷たい空気を吸った」「笑い過ぎた」などのささいな刺激をきっかけに、突然咳が出て止まらなくなることがあります。
喘息の人は、咳のほか、息苦しさや「ヒューヒュー」「ゼイゼイ」という呼吸音も現れることがあります。咳喘息の人は、咳以外の症状は通常みられません。
喘息や咳喘息の咳は、市販の咳止め薬では治まりません。それどころか、市販の咳止め薬で悪化する恐れもあります。
3-3.アトピー咳嗽(がいそう)
咳に対する感受性が高くなり過ぎて、普通の会話など、健康な人なら反応しないわずかな刺激によっても咳込んでしまう病気です。
咳のほか、喉のムズムズやイガイガといった違和感やかゆみなども生じることがあります。
4.特定の条件で咳が出る病気
決まった時間や季節、場所など、特定の条件で咳が出る場合に考えられる病気を紹介します。
4-1.喘息、咳喘息
喘息や咳喘息は、アレルギーが原因で発症することがあります。そのため、ホコリが多い場所や動物の近くなど、アレルギーの原因となる物質が存在する場所にいると、咳が出ることがあります。
また、夜間から朝方にかけては、病気により狭くなっている気道が収縮してさらに狭くなることや、冷え込みの影響で、咳が出やすくなります。
喘息や咳喘息では、気温差が大きい季節の変わり目も、咳がひどくなることが多いです。
4-2.花粉症
「毎年春先になると咳が出る」など、特定の季節にだけ咳がひどくなる場合は、花粉症の可能性があります。鼻水や鼻づまり、目やになどの症状もあれば、さらに花粉症を疑います。
花粉症は春の病気というイメージがありますが、ブタクサなど他の季節に花粉を飛ばす植物が原因の場合、春以外の季節にも症状が現れることがあります。
4-3.胃食道逆流症
胃食道逆流症は、胃の入り口の筋肉が緩むことで、胃液や胃の内容物が食道に逆流する病気です。
この逆流によって胃酸が食道を荒らし、胸焼けや呑酸(どんさん:酸っぱいゲップが口元まで上がってくる感じ)といった症状が起こります。
さらに、逆流が喉付近まで達すると、刺激によって咳や喉の痛み、声枯れなどが現れることがあります。
特に食後に咳がひどくなる場合は、胃食道逆流症の可能性を考える必要があります。
【参考情報】『Gastroesophageal reflux disease (GERD)』Mayo Ckinic
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/gerd/symptoms-causes/syc-20361940
5.体調は悪くないのに咳が出る理由
咳は、必ずしも体調が悪いときだけに出るわけではありません。
さまざまな刺激によって、健康な状態でも咳が出ることがあります。
5-1.空気の乾燥
空気が乾燥すると、喉や気道などの粘膜も乾燥します。すると、刺激への抵抗力が弱くなるため、咳が出やすくなります。
また、喉が乾燥した状態が続くと、異物への防御機能が低下するため、ウイルスや細菌に感染しやすくなります。
5-2.寒暖差
暖かい室内から外へ出て、冷たい外気を吸い込むと、気道が刺激されて咳が出ることがあります。
また、寒暖差で鼻の粘膜が刺激されると、鼻水が出やすくなりますが、鼻水が喉に流れ込むと喉が刺激され、咳が出ることがあります。
5-3.喫煙
タバコに含まれている化学物質の刺激で咳が出ることがあります。
さらに、タバコを吸い続けていると、粘りのある痰が増え、それを排出しようとして咳の回数が増え、慢性化することがあります。
長期間喫煙を続けると、異物を排出する役割を持つ気道の線毛が失われ、ウイルスや細菌に対する防御力が低下します。
その結果、体内にウイルスや細菌が侵入しやすくなり、感染して咳が引き起こされることもあります。
【参考情報】『喫煙と呼吸器疾患』e-ヘルスネット|厚生労働省
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/tobacco/t-03-003.html
5-4.心因性咳嗽
ストレスや緊張などの精神的な要因によって、引き起こされる咳です。
日中や緊張した場面で咳が出る一方、何かに集中している時には咳が出にくいのが特徴です。
6.咳とともに血痰が出る病気
咳と一緒に血痰が出ると驚く方も多いでしょう。血痰が続くようなら、早めに原因を特定し、適切な治療を受けることが大切です。
6-1.呼吸器感染症
風邪やコロナなどの呼吸器感染症で咳をしすぎると、気道が傷ついて痰に血が混じることがあります。
感染症は通常1週間程度で改善することが多く、それに伴い血痰もほとんどの場合おさまります。
6-2.肺がん
肺がんによる血痰は、がんができる場所によって現れる時期が異なります。
気道に近い部分にがんができた場合、早い段階から咳や痰、血痰が出やすくなります。
一方、気道に近い部分以外にがんができた場合は、症状が進行してから血痰が現れるため、発見された時には病状が進んでいることがあるかもしれません。
6-3.肺結核
肺結核の初期症状は風邪に似ていますが、咳は2週間以上続き、徐々に倦怠感や体重減少などの症状が現れます。
さらに重症化すると、血痰や胸の痛み、息苦しさが現れることがあります。
7.呼吸器内科で行う検査
変な音がする咳や、いつもと違うような咳が気になるときは、呼吸器内科を受診しましょう。
問診や診察の結果、必要に応じて下記のような検査を実施します。
7-1.画像検査
X線(レントゲン)やCT(コンピューター断層撮影)で肺を撮影して画像を確認します。
肺に炎症や腫瘍などの異常があると、その部分が白っぽく写ります。
7-2.血液検査
感染症やアレルギーに関連する血液の成分を調べて、診断に役立てます。
感染症にかかると、白血球や炎症の数値が上昇します。
アレルギーが疑われる場合は、アレルゲンに対する抗体の有無を調べます。
7-3.呼吸機能検査
専用の医療機器を使って、肺や気道を調べる検査です。スパイロメトリーやモストグラフなどの検査方法があります。
喘息や咳喘息などの病気が疑われる場合に行われることが多く、検査結果を基に病気の診断や重症度の判定が行われます。
7-4.その他の検査
その他、喀痰検査や抗原検査、迅速検査など、疑われる病気に応じた検査があります。
8.咳が気になるときの対処法
咳を一時的に和らげたい場合は、以下の方法を試してください。
ただし、咳が長引いていたり、対処法を試しても改善しない場合は、病院で診察を受けて原因を調べることが大切です。
8-1.水分を摂る
喉の乾燥は刺激となり、咳を引き起こす原因になります。特に冬は空気が乾燥しやすいため、こまめに水分を摂り、喉を潤しましょう。
冷たい飲み物は喉への刺激が強いので、常温や温かい飲み物を選ぶとよいでしょう。
8-2.部屋を加湿する
部屋の湿度を適切に保つと喉が潤い、空気の乾燥による刺激が少なくなります。
理想的な湿度は40%~60%です。加湿器があれば使用し、ない場合はタオルや洗濯物を干すと湿度が上がります。
8-3.ハチミツの摂取
ハチミツには咳を抑える効果があるとされています。咳がひどいときは、スプーン1杯のハチミツをなめたり、お湯に溶かして摂取してみてください。
ただし、1歳未満の子どもには絶対にハチミツを与えないでください。乳児ボツリヌス症を引き起こす危険があります。
【参考情報】『Effect of honey, dextromethorphan, and no treatment on nocturnal cough and sleep quality for coughing children and their parents』PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18056558/
8-4.喉を温める
外の空気で喉が冷えると咳が出やすくなります。寒い季節に外出するときは、マフラーやネックウォーマーを使って喉を温めましょう。
9.おわりに
風邪とは異なる咳が出たり、咳に違和感を覚える場合、その原因として呼吸器の病気やアレルギーなどが考えられます。
咳が2週間以上続いていたり、治ったと思っても繰り返している場合は、呼吸器内科を受診して原因を調べてみましょう。
アレルギーが原因の場合、市販薬ではなかなか症状が改善されません。また、血痰が出る場合は深刻な病気の疑いがあるので、早めに専門医に相談し、適切な診断と治療を受けることが重要です。