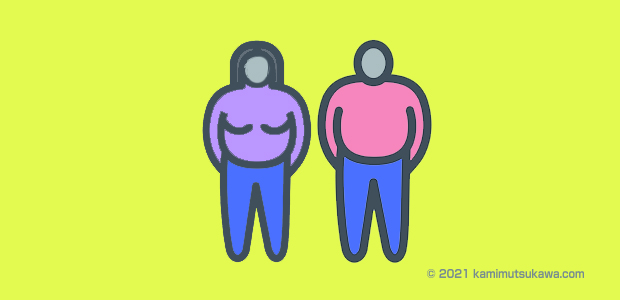睡眠時無呼吸症候群は自分で治せる?原因別の対処法と治療について

家族やパートナーから「いびきがうるさい」と指摘されたり、昼間の眠気がひどくて仕事に支障をきたしている人は、睡眠時無呼吸症候群の可能性があります。
この病気は、さまざまな要因で発症するのですが、生活習慣の改善によって、いびきや無呼吸などの症状を軽減できる可能性はあります。
この記事では、睡眠時無呼吸症候群に対する原因別の対処法や、病院での治療について解説します。治療以外にも、できることがあれば試してみたい方は、ぜひ読んでください。
◆その「いびき」「昼間の眠気」睡眠時無呼吸症候群の初期症状では?>>
目次
1.睡眠時無呼吸症候群とはどんな病気か
睡眠時無呼吸症候群とは、寝ている間に呼吸が止まったり浅くなったりすることを繰り返す病気です。
代表的な症状は、いびきや起床時の頭痛、日中の眠気などですが、治療をせずに放っておくと動脈硬化が進み、脳卒中や心筋梗塞など命にかかわる合併症を起こす危険があります。
成人男性の約3~7%、女性の約2~5%に見られる病気で、男性では40歳~50歳代が半数以上を占め、女性では閉経後に増加する傾向があります。
【参考情報】『睡眠時無呼吸症候群/SAS』厚生労働省e-ヘルスネット
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/heart/yk-026.html
【参考情報】『睡眠時無呼吸症候群』日本呼吸器学会
https://www.jrs.or.jp/citizen/disease/i/i-05.html
◆「睡眠時無呼吸症候群の原因|なぜ睡眠中に気道が狭くなる?」>>
2.睡眠時無呼吸症候群は自力で治せるのか
睡眠時無呼吸症候群は、完治は難しい病気です。しかし、CPAP(シーパップ)をはじめとした治療により、症状を軽減することはできます。
また、症状を悪化させている原因に対処することで、治療の効果を上げることは可能です。
3.睡眠時無呼吸症候群・原因別の対処法
症状を軽減させるためには、原因別に下記のような対処法が有効です。
3−1.肥満
肥満の人は、気道の周囲に脂肪が蓄積しているため、気道が狭くなっています。そのため、空気が通りにくくなり、無呼吸やいびきなどの症状が起こりやすいのです。
アメリカの研究では、4年間で体重が10%増えると無呼吸低呼吸指数(AHI)が32%増加し、10%減るとAHIが26% 減少すると予測されると報告されています。
【参考情報】『Weight Loss Is Integral to Obstructive Sleep Apnea Management. Ten-Year Follow-up in Sleep AHEAD』National Library of Medicine
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7874406/
【参考情報】『Obstructive Sleep Apnea and Obesity: Implications for Public Health』NCBI
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5836788/#:~:text=Obstructive%20sleep%20apnea%20syndrome&text=In%20obese%20people%2C%20the%20narrowing,apnea%20and%20hypoxia%20%5B26%5D.
肥満は、不規則な食事や運動不足などが原因で、体脂肪が蓄積されることによって起こることがほとんどです。
思い当たる方は、まずは毎日の食生活を見直してみましょう。
◆「睡眠時無呼吸症候群は減量で改善する?肥満との関係や減量のコツについて」>>
3−2.飲酒
アルコールには筋肉を緩める作用があります。
【参考情報】『アルコールの作用』厚生労働省e-ヘルスネット
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/alcohol/a-02-003.html
睡眠時無呼吸症候群の人は、もともと気道が狭くなっています。そのため、アルコールで気道周囲の筋肉がゆるむとさらに気道が狭くなり、無呼吸やいびきなどの症状がひどくなります。
お酒が好きな人は、睡眠時無呼吸症候群の治療を受けたうえで、「適度な量」「寝酒はしない」ことを意識して楽しみましょう。
3−3.喫煙
タバコには多くの有害成分が含まれており、喫煙習慣がある人は慢性的な気道の炎症を起こしています。そのため、気道がむくんで狭くなり、睡眠時無呼吸症候群を引き起こす原因となるのです。
症状の悪化を防ぐには、禁煙することを強くおすすめします。禁煙外来で相談するのもいいでしょう。
3−4.睡眠薬
睡眠薬には、筋肉を緩める作用を持つものが多く、服用すると気道周囲の筋肉がゆるんで、舌がのどへ落ち込みやすくなります。すると、睡眠時無呼吸症候群の症状が悪化することがあります。
睡眠時無呼吸症候群の症状がある人が睡眠薬を使いたい場合は、自己判断で市販薬を服用するのは避け、筋弛緩作用のない薬を医師に処方してもらいましょう。
3−5.寝るときの姿勢
いびきや無呼吸で睡眠が妨げられる人は、横向きやうつぶせなど、舌が落ち込みにくい姿勢で眠ることで、症状が軽減することがあります。
重症の患者さんにはあまり効果は期待できませんが、軽症〜中等症の患者さんは、一度試してみるとよいでしょう。
4.睡眠時無呼吸症候群の検査
睡眠時無呼吸症候群の診断には、専用の装置を用いた検査が必要となります。病院を選ぶ際には、ホームページなどで検査ができるかどうかを確認しておきましょう。
4−1.簡易検査
問診で病気の疑いがあると判断されたら、睡眠中の呼吸状態を調べるために、アプノモニターという小型の装置を自宅に持ち帰って簡易検査を行います。
アプノモニターでの簡易検査の結果、無呼吸低呼吸指数(AHI)が5未満であれば睡眠時無呼吸症候群ではないと判断され、40を超えると重症のためすぐに治療を開始します。
簡易検査でさらに疑いがあれば、精密検査を行います。
4−2.精密検査
精密検査では、ポリソムノグラフィー(PSG)という検査を行います。
ポリソムノグラフィーでは、体に様々なセンサーをつけて一晩、以下のような項目をチェックします。
・脳波
・眼球運動
・筋電図
・心電図
・血液中の酸素の量
・鼻や口の中の空気の流れ
・胸部や腹部の動き
・いびきの音
精密検査は、医療機関や検査施設に一泊して行うことがほとんどですが、当院では入院せずに自宅で検査を受けることが可能です。
5.睡眠時無呼吸症候群の治療
睡眠時無呼吸症候群はCPAPなどの様々な医療機器を用いて治療を行います。
ここではそれぞれの治療法と、その効果や特徴を解説いたします。
睡眠時無呼吸症候群の治療法でお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
5-1.CPAP療法(持続陽圧呼吸療法)
CPAP療法は、就寝中の気道を開いた状態で維持することで、正常な呼吸を促進します。呼吸がスムーズに行えることにより、酸素の供給が改善され、睡眠中の無呼吸の対策が可能です。
CPAP療法を継続して行うことにより、患者さんの日中の眠気や疲労感を減らし、交通事故などのリスクを減らすことができます。
心血管系への影響、代謝異常のリスクを減らすことができ、肥満や糖尿病のリスクも減少できます。
CPAP療法は、睡眠時無呼吸症候群の症状に対する効果的な治療法であり、患者さんの生活の質を向上させることが期待できます。
◆「睡眠時無呼吸症候群になると認知症のリスクが上がる?」>>
5-2.マウスピース(口腔内装置)療法
マウスピース療法は、睡眠時にマウスピースを装着し、下あごを前方に固定して空気の通り道を開くようにする治療法です。軽症~中等症の患者さんに適用されます。
主にCPAP療法の適用が困難な方に適用され、睡眠時無呼吸症候群の場合、保険適用で作成することができます。
小さくて持ち運びに便利なため、主張先や旅行先でも気軽に使用することができます。
効果はCPAP療法に比べ限定的ですが、装置の負担が少なくストレスになりにくいのが特徴です。
【参考記事】『マウスピース』無呼吸なおそう/TEIJIN
https://659naoso.com/medical/treatment/mouthpiece
5-3.ASV療法
CPAP・マウスピースの他に新しい治療法として確立されたのがASV療法です。
ASVはCPAPのように装置を着装し、酸素を送り込む治療法です。
しかし、CPAPとの違いはCPAPが「酸素を一定のリズムで送り込む装置」であるのに対し、ASVは「患者の呼吸に合わせて適切な量の酸素を送り込む装置」であることです。
特に心臓の病気などで呼吸のリズムが不規則な患者さんにはASVが適しています。
【参考情報】『Basics of Sleep Apnea and Heart Failure』American College of Cardiology
https://www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2014/07/22/08/25/basics-of-sleep-apnea-and-heart-failure
5.おわりに
睡眠時無呼吸症候群は、正しい治療を続けていれば、多くの場合症状が激減していきます。ぐっすり眠り、スッキリ目覚める生活を目指して、ぜひ治療を続けていきましょう。
さらに、生活習慣の改善に取り組めば、症状の軽減が期待できるとともに、心筋梗塞などの合併症を防ぎ、さらに高血圧や糖尿病などの生活習慣病の悪化も防ぐことができます。