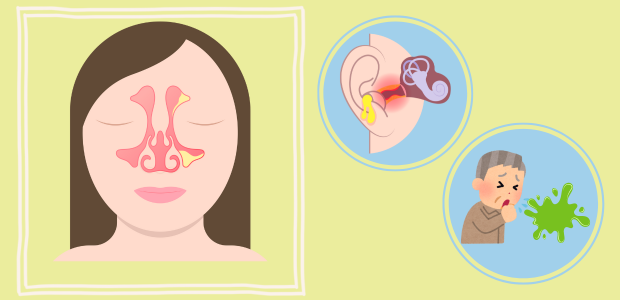花粉症の症状~似ている病気や他のアレルギーとの違い

春先にくしゃみや鼻水が出てきたら、「花粉症では?」と疑う人も多いでしょう。
しかし、くしゃみや鼻水は風邪の症状でもありますし、風邪以外にも花粉症と同じような症状が出る病気はあります。
この記事では、花粉症の症状を説明しながら、風邪や他の病気・アレルギーとの違いを説明していきます。「花粉症かもしれない」と不安に思っている人は、ぜひ読んでください。
目次
1.花粉症の症状
花粉症とは、スギやヒノキなどの植物の花粉が粘膜に触れることによってアレルギー症状を起こす病気です。
主な症状は目と鼻に現れます。鼻の三大症状はくしゃみ・鼻水・鼻づまり、目の三大症状は目のかゆみ・充血・涙です。
ほかにも、皮膚やのどのかゆみ・咳・頭痛、頭重感・発熱・イライラ・食欲不振・下痢といった症状があらわれる人もいます。
また、後述するように、花粉症は「季節性アレルギー」のアレルギー性鼻炎に分類されていますが、スギ・ヒノキ花粉が飛ぶ春に限らず、イネ科の花粉は夏ごろ、ブタクサの花粉は秋ごろが飛散時期となっています。
このように花粉症の原因となる花粉の種類はたくさんあり、人によっては複数の花粉が原因でアレルギー症状が起きる人もいます。
2.花粉症と風邪の見分け方
花粉症と風邪の初期症状はよく似ています。しかし風邪の場合、くしゃみや鼻水などの症状は長くても1週間程度で治まるのに対し、花粉症では花粉が飛散している3~4か月の間、ずっと続きます。
風邪の時の鼻水は、やや黄色味を帯びていて粘り気がありますが、花粉症では透明でサラサラした鼻水が大量に出ます。
また、花粉症のくしゃみは何度も続けて出ます。鼻の症状が出ると呼吸がしづらくなることがあり、集中力が欠けてしまうなどの弊害もあります。
くしゃみも鼻水も、特に朝起きた時にひどく出る傾向が見られます。この現象は「モーニングアタック」と呼ばれています。
風邪では目の症状は現れないので、鼻の三大症状があると同時に、目のかゆみや違和感があったら、花粉症の可能性が高いでしょう。このような花粉症の症状は、花粉の飛散量に比例して強くなるといわれています。
3.花粉症と似た症状がある別の病気
くしゃみや鼻水、目のかゆみがあっても、花粉症とは限りません。別の病気やアレルギーで、似たような症状が引き起こされていることがあります。
3-1.インフルエンザ
インフルエンザにかかると、38℃以上の高熱や寒気、関節痛、筋肉痛、全身のだるさなどが急激に強く現れます。
インフルエンザでもくしゃみや鼻水が出ることはありますが、高熱や体の痛みの後、遅れて出てくるのが特徴です。
3-2.アレルギー性鼻炎
アレルギー性鼻炎は、体の中にアレルギーの原因物質が侵入して鼻の粘膜に炎症を起こし、くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどの症状を引き起こす病気です。喘息やアトピー性皮膚炎など、アレルギー性の病気を持つ人に起こりやすいと言われています。
◆「喘息の悪化を招く鼻炎!合併しやすい理由と治療での改善について」>>
アレルギー性鼻炎は、季節を問わず一年中症状が現れる「通年性アレルギー」と、特定の時期だけ症状が現れる「季節性アレルギー」に分けられます。そして花粉症は、季節性アレルギーに分類されます。
【参考情報】『アレルギー性鼻炎』日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会
https://www.jibika.or.jp/modules/disease/index.php?content_id=21#arerugi
通年性アレルギーの主な原因は家の中のホコリ(ハウスダスト)、ダニ、カビ、猫や犬などペットの毛です。花粉症のシーズンが終わっても鼻の症状が治まらない時は、アレルギー科のある病院を受診すると、アレルギーの原因物質を特定する検査を受けることができます。
3-3.副鼻腔炎(蓄膿症)
副鼻腔(ふくびくう)とは、鼻の周囲にある骨に囲まれた空洞です。副鼻腔炎とは、ここに風邪などのウイルスや細菌が感染して膿が溜まったり、鼻づまりや鼻水などの症状が現れる病気です。俗に「蓄膿症」とも呼ばれます。
花粉症の鼻水はサラサラですが、副鼻腔炎が慢性化すると、粘り気のあるドロッとした鼻水が多くなります。色も黄色や緑に変わり、嫌なにおいがすることもあります。炎症がのどに広がると、咳や痰も出てきます。
副鼻腔炎は、通常は1~2週間程度で治りますが、長引いたり、繰り返すことによって、慢性化する恐れがあります。また、頭痛や歯痛、中耳炎などを引き起こすこともあるので、疑わしい症状がある時は、早めに病院を受診しましょう。
【参考情報】『Sinus Infection (Sinusitis)』Cleveland Clinic
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/17701-sinusitis#:~:text=Sinusitis%20is%20an%20inflammation%2C%20or,clean%20and%20free%20of%20bacteria.
3-4.結膜炎
結膜とは、白目の表面からまぶたの裏側までをおおっている粘膜です。ここが炎症を起こすと、目が充血したり、かゆくなったり、涙が出ることがあります。
結膜がウイルスや細菌に感染した時や、ダニやカビ、ハウスダストなどアレルギーを起こす物質が原因となって症状が現れます。また、コンタクトレンズについた汚れから、アレルギーが引き起こされることもあります。
アレルギーによって起こる結膜炎は、年間を通して症状が現れる「通年性アレルギー」と、特定の時期だけ症状が現れる「季節性アレルギー」に分けられます。花粉症による目の充血やかゆみは、季節性アレルギー結膜炎に分類されます。
花粉症のシーズンが終わっても目の症状が治まらない時は、アレルギー科のある病院を受診すると、アレルギーの原因物質を特定する検査を受けることができます。また、花粉のシーズン中でも、目の痛みが強かったり、のどの痛みや発熱なども同時にある時は、早めに病院を受診しましょう。
【参考情報】『アレルギー性結膜炎』アレルギーポータル|日本アレルギー学会
https://allergyportal.jp/knowledge/allergic-conjunctivitis/
3-5.寒暖差アレルギー(血管運動性鼻炎)
気温の急激な変化によって自律神経のバランスが乱れ、くしゃみ・鼻水・鼻づまりといった症状が現れる病気です。一般的には「寒暖差アレルギー」として知られていますが、正式には「血管運動性鼻炎」といいます。
寒暖差「アレルギー」という名称から、アレルギー性疾患であるように誤解されがちですが、花粉・ハウスダストなどのアレルゲンとは関係なく発症します。
治療には、症状を和らげるための抗ヒスタミン薬や点鼻薬が用いられることがあります。また、自律神経のバランスを整えるために、生活習慣の改善が有効とされることもあります。
4.花粉症の検査
花粉症の検査には、以下のようなものがあります。
・血中総IgE値測定:アレルギーの有無や程度を調べる
・特異的IgE検査:アレルギーを引き起こす物質を調べる
・プリックテスト:皮膚にアレルゲンを入れて反応をみる
・鼻汁好酸菌検査:鼻汁に含まれる好酸球の量を調べる
・細隙灯顕微鏡検査:眼の状態を確認する
これらの検査を組み合わせることで、花粉症の診断や重症度の評価が可能となり、適切な治療方針を決めるのに役立ちます。
5.花粉症の治療
医療機関での花粉症治療には、症状を和らげる対症療法と、病気の原因に働きかける根治療法の2種類があります。
対症療法では、抗アレルギー薬や抗ヒスタミン薬を使ってアレルギー反応を抑え、症状を軽減します。さらに、ステロイドの点鼻薬・点眼薬や、鼻の粘膜を焼いて反応を抑えるレーザー治療も選択肢の一つです。
根治療法としては、アレルゲン免疫療法があります。これは、原因物質を少しずつ体に取り入れ、徐々に慣らすことで症状を出にくくする治療法です。ただし、適用はスギ花粉アレルギーに限られています。
花粉症を発症したら、できるだけ花粉を吸い込まないようにマスクを着用し、こまめにうがい・手洗いをすることが大切です。
鼻や目を洗浄して付着した花粉を洗い流すのも効果的ですが、水道水には塩素が含まれているため、鼻や目を傷つける恐れがあります。
目を洗うときは防腐剤が入っていない人工涙液、鼻を洗うときは専用の洗浄液を使用しましょう。
6.おわりに
今後、地球温暖化の影響で、花粉の飛散数がさらに増加すると予想されています。「風邪かな?」と思っていたのに、いつまでもくしゃみや鼻水が出ている時は、花粉症または他の病気・アレルギーを疑ってみましょう。
花粉症も他のアレルギーも、症状が軽いうちに治療を始めると、症状をコントロールしやすくなります。また、自律神経が乱れるとアレルギー反応を起こしやすくなるので、ストレスや生活習慣の乱れも大敵です。