

精神保健福祉士とは、精神疾患や心の悩みを抱えている人々が地域で負担なくスムーズに生活出来るように、相談に乗ったりアドバイスをしたり社会参加の手助けをする仕事です。
精神保健福祉士は1997年の精神保健福祉士法の施行に伴って誕生した専門職の国家資格です。社会福祉士、介護福祉士に次ぐ福祉系の三大国家資格の1つで介護施設や福祉施設を中心に沢山の職場で活躍ができる資格です。
今回の記事では精神保健福祉士の役割や資格の取得方法、さらにはキャリアアップについてなどを紹介していきたいと思います。
1.精神保健福祉士の役割とは?

精神保険福祉士は精神疾患を抱える方やその家族が抱えている問題を解決するために、相談にのったり環境調整を行い、地域や社会と繋ぐ重要な役割を担っています。
1.1 精神保健福祉士の仕事内容
精神保健福祉士の主な仕事内容としては、精神的な障害を抱えた人の相談にのり、その方たちが望む暮らしが出来るように一緒に問題を解決したり、地域社会との繋がりを持てるように支援したり、社会復帰の手助けを行ったりします。
必要に応じて障害者手帳の申請や生活保護の手続きなど、法的・行政的な手続きも支援します。
また本人だけでなく周りで支える家族の支援も行います。ただ、勤務する場所によって仕事内容は異なるのでどのような職場に勤務するかによって実際に行う仕事は変わってきます。
1-2.活躍する職場
精神保健福祉士が活躍する職場は多岐に渡ります。
医療機関や行政機関、障がい福祉サービス事業所、高齢者福祉施設、児童養護施設など様々な場所で活躍しています。ファミリーグループのデイサービス施設であるブルーミングケア小机でも活躍頂けます。
医療機関では精神病院や総合病院の精神科や心療内科などで働く方が多いです。患者様の入院や退院のサポートや、入院生活中のサポートを医師などと相談しながら行ったりします。また退院後も社会と繋がりを持ちながら日常生活が送れるようサポートを行います。
行政機関での仕事は主に地域の保健所や福祉事業所、精神保健福祉センターなどが勤務場所になります。精神的に悩みを抱えた人達の相談にのったり、安心して社会とつながりを持てる機会をつくります。
また、日常生活がスムーズにを送れるよう就労支援を行ったり、利用できる公的支援制度を紹介する業務に携わります。また、精神障がい者への偏見をなくすことや、精神障がい者を支える家族の偏見をなくすことを目的としたメンタルヘルスの啓発活動を行うことも仕事のうちのひとつです。
ブルーミングケア小机のような高齢者施設では精神保健福祉士の資格をもっている方は生活相談員として活躍していただく事が出来ます。生活相談員とはデイサービス施設には必要不可欠な職種で、デイサービス施設の窓口対応が主な仕事です。
利用者の方やそのご家族への対応や、各分野の専門家の方たちと連携をとりながら利用者の方にとってより良い介護サービスが提供できるようにするとても重要な役割がある職種です。精神保健福祉士の資格を持っている方にはそのような重要なポジションで活躍をして頂くことが出来ます。
上記の場所以外にも精神的に悩みを抱える人を支え地域社会とつながりをもてるよう様々な職場で活躍しています。
2.精神保健福祉士資格を取得するメリット

精神保健福祉士の資格を取得することで多くのメリットがあります。
2.1 専門性の証明
精神保健福祉士は国家資格のうちの一つです。
精神保健福祉に関する専門性を持つことが認められます。資格を持っていることにより医療機関や福祉施設で信頼を得やすくなります。
2.2 多様なキャリアパス
精神保健福祉士の資格を取得すると様々な場所で活躍できる可能性が広がります。
医療機関、福祉施設だけでなく行政や教育機関など様々なフィールドで活躍できます。
2.3 社会貢献度の高さ
近年精神疾患や心の問題に悩む方々が増加しています。
また高齢社会が進む中で高齢者施設の需要が増えています。そのような時代で精神保健福祉士として働くことは、社会に大きく貢献する仕事です。
利用者からの感謝や社会復帰を見届けることが、やりがいにも大きく繋がります。
3. 精神保健福祉士資格の取得方法

精神保健福祉士の資格を取得するには、所定の学歴や実務経験を満たし、国家試験に合格する必要があります。
3.1 資格取得までのルート
精神保健福祉士の資格を取得するにはいくつか方法があります。
まず一つ目は保健福祉系の4年制大学で指定科目を学び卒業することで受験資格を得ることが出来ます。
二つ目は保健福祉系の短大で指定科目を学んで卒業した人は、実務経験をすることで受験資格を得ることができます。必要な実務経験の年数は、3年制の短大で1年、2年制の短大で2年となっています。
保健福祉系大学などで基礎科目のみ修了している場合は、短期養成施設などで6ヶ月以上学ぶ必要があります。
4年制の場合はそのまま短期養成施設などに入学することも可能です。
短大の場合は、指定科目修了者の受験資格と同様の相談援助に関する実務経験(3年制の短大で1年、2年制の短大で2年)を積むことで短期養成施設へ入学することが出来ます。
また、社会福祉士の資格を取得している場合は、学歴は関係なく、相談援助の実務経験がなくても短期養成施設などへの入学が可能です。
最後に一般大学や短大を卒業した人や、相談援助に関する実務経験が4年以上ある人の場合は一般養成施設などで1年以上学ぶ必要があります。4年制の一般大学卒業の場合は実務経験は必要ありません。一般短大などの場合は実務経験が必要となります。
3.2 国家試験の概要
精神保健福祉士の国家試験はマークシート形式で17科目が出題される筆記試験です。
また合格基準点は全体で60%以上の正解率、17科目すべてで正解をしていることが基準となります。合格率は60%程度になります。
3.3 試験対策のポイント
試験対策のポイントとしては、自力でテキストや過去問を用意し勉強を進めていく方法。
一方、試験対策講座であれば、費用は高額になりますが、専門講師の指導に沿って万全の対策を取ることができます。
4.精神保健福祉士としてのキャリアアップ

精神保健福祉士の資格を取得をした後はキャリアアップに繋げることが出来ます。様々な資格と組み合わせることで新たな可能性を広げることができます。
例えば社会福祉士や介護福祉士などの福祉系の資格と組み合わせることで、幅広い福祉分野で活躍することが可能です。
また臨床心理士の資格と合わせるとカウンセリングや心理療法に特化した支援ができるようになります。近年は企業の産業保健部門で、社員のメンタルヘルスケアを担当するポジションも増えています。
5. 精神保健福祉士の今後の需要と展望
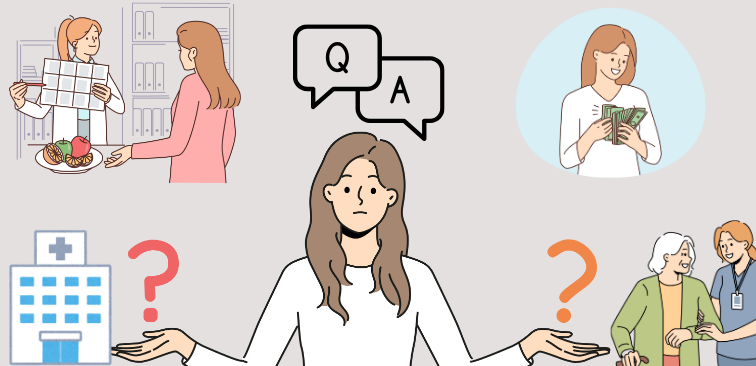
精神保健福祉士は、現代社会においてどのような役割を担っているのでしょうか?社会情勢に伴う需要や今後の新しい活躍に期待されています。
5.1 需要の高まり
近年、日本はストレス社会であり精神疾患や悩みを抱えている人が増加しています。
心の問題を抱えた方が増えている分、精神保健福祉士の需要はますます高まっています。
精神的に不安を抱えた人の悩みを聞くだけでなく今後は精神疾患を持った方が自立した社会生活を送るためのサポートを行う施設も増加していくことが考えられ、今後も活躍の場が益々広がることが予想されます。
5.2 ICTやテクノロジーとの融合
近年は直接患者さんと話して支援するだけでなく、オンラインカウンセリングやデジタルツールを活用した支援方法が普及しつつあります。
直接顔を合わせて話すのが苦手な精神疾患を抱えた人も相談しやすくなるメリットもあります。時代に合わせて様々なツールを使い活躍できる新しい働き方が生まれています。
6. まとめ
精神保健福祉士は精神疾患を患う人がどんどん増えている今後の日本の生活の中ではとても重要な資格になると言えます。
活躍出来る場面は多岐に渡り、医療機関、福祉施設、教育機関、行政など様々な分野で活躍出来る資格となります。
そして当グループのブルーミングケア小机でも活躍して頂ける資格です。是非介護にも興味があり、精神保健福祉士の資格を取得されている方は当院で働きませんか?