

亜鉛は、肌や髪の健康維持に役立つ栄養素であり、免疫機能にまで活躍する栄養素でもあります。
風邪や感染症予防にも繋がる亜鉛は、この時期にとてもおすすめしたい栄養素の1つです。
今回の記事では、亜鉛についてご紹介したいと思います。
1.亜鉛とは?
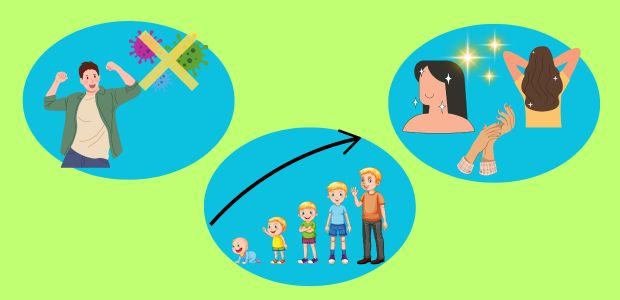
亜鉛とは、必須ミネラルで体内で重要な役割を果たしています。
免疫機能や代謝、さらに肌や髪の健康にも関わっていて、健康な生活を送るうえで欠かせない栄養素です。
しかし、現代の食生活では亜鉛が不足している人が多いとされています。
1-1成分
成分は、カルシウムやマグネシウムなどのミネラルの1つで、体内に約2グラムとごくわずかしか存在しない「微量ミネラル」の1つです。
体内で合成できないので、食事で補う必要があります。
1-2主な働き
亜鉛の効果は全身に働きかけています。主な働きは以下の通りです。
アレルギーを抑制、風邪予防
免疫細胞である白血球を増やして、免疫の働きを固める作用があります。亜鉛を摂取すると免疫細胞の活性が強まり、免疫が十分に働くので、風邪が引きにくくなります。
成長と発達
細胞分裂やDNAの合成に必要不可欠な栄養素で、子どもの成長や発達に重要です。骨を丈夫にする働きもあります。
皮膚や髪、爪の健康維持
皮膚の新陳代謝を促し、傷の治療も助ける効果があります。髪や爪の健康にも関わってきます。
2.亜鉛不足のリスク

亜鉛は不足することでさまざまなリスクを伴います。
2-1 亜鉛不足からの症状
亜鉛不足によって起こる症状として、免疫力の低下があります。免疫細胞の活性が弱まってしまうため、風邪を引きやすくなり、感染症にもかかりやすくなります。
味覚の障害も引き起こすことがあり、味覚が鈍くなることや食べ物の味が感じることができないということもあります。
味覚障害は、舌の表面にある味蕾(みらい)の機能が低下することで起こります。味蕾は新陳代謝が活発な細胞であるため、その再生には亜鉛が必要です。
肌や髪のトラブルにも繋がり、肌荒れや乾燥、抜け毛が増えることがあります。
爪への影響もあり、もろくなってしまうことがあります。骨にも影響があり、筋肉に60%、骨に30%含まれているといわれ、不足すると骨粗鬆症が進行するともいわれています。
そして、特に男性は亜鉛不足によって精子の量や質に影響することがあり、不妊症のリスクにも繋がります。
女性は妊娠中、授乳中だと亜鉛不足には気をつけないといけません。妊娠中の亜鉛不足は赤ちゃんの正常な発育に影響を与える可能性があります。
授乳中は母乳を通じて赤ちゃんに送られる栄養素なので、健全な発育に欠かせません。
2-2 亜鉛不足の原因
亜鉛不足の原因として、過度なダイエットやファストフード、偏食、加工食品の摂りすぎ、亜鉛の吸収を阻害する影響のあるアルコールの過剰摂取などの食生活の問題、過度な運動があります。
他にも降圧剤、利尿剤、解熱鎮痛剤、抗菌剤、糖尿病治療薬などの薬の副作用、長期的なストレスが挙げられます。
3.亜鉛の推奨摂取量と過剰摂取のリスク

亜鉛を摂れば摂るほどいいというわけではありません。
推奨摂取量は決められており、過剰摂取によるリスクもあります。
3-1 推奨摂取量
日本人の食事摂取基準(2020年版)によると、男性は1日に18~69歳は10mg、70歳以上は9mgで、女性は18~69歳は8mg、70歳以上は7mgが推奨されている摂取量です。
妊娠中や授乳中の女性は、さらに1~2mg加えて摂取することを推奨されています。
3-2 過剰摂取の症状
亜鉛を過剰に摂取することで、吐き気や嘔吐、下痢、食欲不振、頭痛などの症状が出る可能性があります。
長期にわたって摂取が続くと、銅の吸収が低下してしまうため貧血や免疫力の低下にも繋がる恐れがあります。
4.亜鉛を含む食品と効率的な摂取方法

亜鉛は食品から摂取することが理想的ですが、サプリメントでも補うことができます。
亜鉛を多く含む商品と効率的な摂取方法があるので、ご紹介します。
4-1 亜鉛を多く含む食品
動物性食品では牡蠣、牛肉、卵黄が亜鉛が多い食品です。
牡蠣は亜鉛の含有量が非常に高く、効率的に摂取ができます。
牛肉だと赤身肉に豊富な亜鉛が含まれています。卵にも含まれているので、手軽に摂取ができます。他にも豚レバー、ホタテ貝、うなぎなどが挙げられます。
植物性食品では、納豆や豆類、ごまやナッツ類、海藻類があります。
大豆製品には亜鉛が含まれています。ごまやナッツ類だとスナック感覚で手軽に摂取できることが魅力だといえます。海藻類はわかめや昆布に含まれています。
亜鉛が多く含まれている食品を紹介しましたが、偏ってこれらの食品ばかり食べることはおすすめできません。
一汁三菜の食事を心がけると亜鉛は十分量摂取できるので、加工食品やレトルト食品を利用することもあるかと思いますが、何か1品自炊するなどの工夫をすることが大切です。
4-2 効率的な摂取方法
効率的な摂取方法として、亜鉛の吸収を高めるビタミンCと一緒に摂ることです。
野菜やフルーツと組み合わせた食事がおすすめです。
調理方法は焼いたり蒸したりすることで亜鉛を逃がさず摂取することができます。また、水にも溶けやすいので、汁物やスープにすることもよいでしょう。
4-3 サプリでの取り入れ方
適切な量を必ず守り、過度に摂取してしまわないように1日の推奨摂取量に合った製品を選びましょう。
品質も大事で、信頼性のあるメーカーの製品を選びましょう。
食事の代わりにはならないので、あくまで補助として利用してください。
医師や管理栄養士に相談し、自分に合った製品を選ぶようにしましょう。
5.この時期に亜鉛をお勧めする理由

亜鉛は体内の必要不可欠な栄養素の1つですが、注目される効能として肌の健康や潤いを保つ機能があります。
皮脂の生成を正常化して、べたつきやテカリを抑えることや、抗菌効果で肌荒れを防ぎ、肌を清浄に保つなどの効果があります。
肌が乾燥し、肌の健康が揺らいでしまう今の時期には特におすすめしたい栄養素です。
6.おわり
当院では管理栄養士による栄養カウンセリングをおこなっています。
この時期には肌のトラブルや、免疫力を高めていくためにも亜鉛はカウンセリングのときに紹介をすることが多いです。
食事を通してバランスよく亜鉛を摂取し、必要に応じてサプリメントを利用することで、亜鉛の恩恵を最大限に受けることができます。
健康的な生活を送るためにも、亜鉛を摂ることを意識してみてください。