

春や秋になると、くしゃみや鼻水、目のかゆみといった症状が現れる花粉症。
毎年つらい症状に悩まされ、この時期はお薬を服用される方も多いのではないでしょうか?
実は花粉症の症状は、食生活を見直すことで緩和することができるといわれています。
本記事では、当院で活躍する管理栄養士がおすすめする花粉症対策に効果的な食べ物や栄養素をご紹介いたします。
1. 花粉症対策には食事からのアプローチも重要!
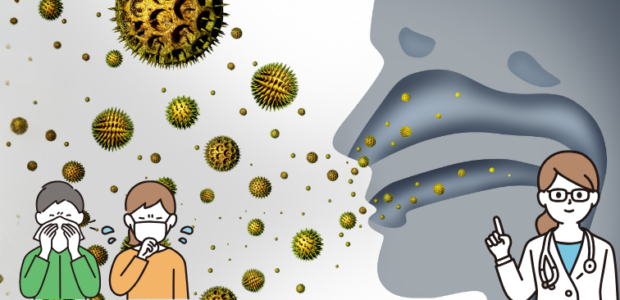
私たちの身体は毎日、口にする食事によって作られています。
とくに、腸内環境は免疫機能と密接に関係していることが明らかになっており、適切な食生活を意識することで免疫力を高めることができるといわれています。
この章では、花粉症の起きるメカニズム、腸内環境と免疫の関係、また花粉症を悪化・軽減させる食事について詳しく解説していきましょう。
1.1 花粉症の起きるメカニズム
花粉症は体内に入ってきた「花粉=異物」に対して人間の身体が起こす免疫反応です。
私たちの身体は、体内に入った花粉を「敵」と認識し、その敵と対抗するための「抗体」を作ります。
再び花粉が体内に侵入してきたときに「敵」を排除しようとする反応、それが「花粉症」です。
花粉症の症状でいうと、「くしゃみ」は花粉を外に出そうとし、「鼻水」や「涙」は花粉を洗い流そうとしています。
また、花粉の種類によっては、咳や喘息が起きたり、口の中がかゆくなるなどの症状が出ることもあります。
一般的に、この免疫反応は身体にとって良いことなのですが、ときにその反応が過剰になってしまい生活に支障をきたすことがあります。
身体にとってマイナスに働いてしまうアレルギー反応となってしまうのです。
1.2 腸内環境と免疫力の関係
腸が「第2の脳」といわれているのはご存じでしょうか?
腸の働きは、食べ物を消化するだけではなく、アレルギーや肥満・免疫力に深く関わっていると言われています。
ここでは、腸内環境と免疫力の関係性をみていきましょう。
<花粉症と腸内環境>
先述した通り、花粉症は免疫反応の1種です。
腸内環境を整えることで免疫力が向上し、花粉症の症状の緩和を期待できます。
腸内細菌のバランスが乱れると、免疫の過剰反応を抑える細胞の働きが弱まり、アレルギー症状が出やすくなります。また、腸内フローラの多様性の低下や乱れが、花粉症の発症に影響を与えていることもあります。
※腸内フローラとは…腸内に生息する多種多様な細菌群のこと。「フローラ」は「お花畑」という意味で、腸内に存在する細菌の集まりがまるで花畑のように見えることから、このように呼ばれています。
<花粉症と免疫力>
花粉を異物と認識して抗体を作る「免疫反応」が過剰になり、免疫が低下すると免疫応答の力が弱くなり、花粉症も発症しやすくなります。
風邪や副鼻腔炎、咽頭炎などの合併症を引き起こし重症化するというリスクもあるので注意しましょう。
1.3 花粉症と食事の関係
花粉症の症状は、食事の栄養バランスや使用する食材によって悪化したり軽減したりすることがあるため、意識した食生活を心がけることが大切です。
【花粉症を悪化させる4つの代表する食事や行動】
・小麦・乳製品 ⇒腸の粘膜に小さな穴をあけて有害物質が体の中に侵入しやすくなる。
・脂っこいもの・甘いもの・刺激物(辛い食べ物や香辛料など)の過剰摂取
⇒炎症を促進したり、腸内環境を悪化させる
・過度の飲酒(特に日本酒・ビール・ワイン)⇒血管を拡張し鼻詰まりを悪化させる
・喫煙 ⇒煙が、鼻や喉の粘膜を刺激し症状を悪化する
・冷たいものや生もの ⇒身体を冷やし、血流の悪化・免疫力の低下につながる
【花粉症を軽減する食事4選】
・ω(オメガ)-3脂肪酸を多く含む魚介類(特に青魚)
・亜麻仁油やチアシードなどの植物由来のω-3脂肪酸
・タンパク質
⇒炎症を起こしている細胞をきれいなものに変えるためにも、体重×1.5倍量くらい摂取するのがおすすめです。
(例・体重50kgの場合、50✕1.5=75g必要となります。)
・野菜たっぷりの食事でビタミン、ミネラル
過度な摂取を控えたり、必要な食材を積極的に取り入れたり、日常生活の中で少し意識をすることで花粉症を緩和することができますよ。
また、花粉症の種類によっては「交差反応」と呼ばれる現象を起こし、アレルギー症状が悪化することがありますので注意しましょう。
※「交差反応」とは・・・特定の花粉のアレルゲンと特定の食物に含まれるタンパク質の構造が似ているために、身体が間違えて起こしてしまうアレルギー反応のこと。
・カバノキ科(シラカバ)の花粉症:バラ科の果物(リンゴ、モモ、サクランボなど)
・イネ科(ススキ等)、キク科(ブタクサ・ヨモギ等)の花粉症:ウリ科果物(メロン、スイカなど)
キク科花粉症の方は、カモミールなどのハーブにも注意が必要です。
花粉症の時期は、とくに悪化しやすいと言われていますので、控えることをおすすめします。
2.管理栄養士おすすめの花粉症対策に効果的な栄養素と食品

ここからは、当院の管理栄養士がおすすめする花粉症に効果的な栄養素と食品について解説していきます。
2.1 花粉症対策に効果的な栄養素
<抗炎症作用のある「EPA・DHA」>
効果:炎症を抑え、免疫機能を調整
食品:サバ、イワシ、アマニ油、えごま油など
魚に多く含まれるEPA(エイコサペンタエン酸)やDHA(ドコサヘキサエン酸)は、体内の炎症を抑える作用があるので、花粉症の症状を緩和する効果が期待できます。
<腸内環境を整える「乳酸菌・発酵食品」>
効果:免疫機能を正常化し、アレルギー症状を軽減
食品:納豆、味噌、ぬか漬けなど
乳酸菌を含む発酵食品を摂取することで、腸内フローラを整え、免疫バランスを改善することが期待でき、腸内環境を整えてくれます。
また、乳酸菌も大切ですが、「乳酸菌生産物質」を当院ではオススメしております。
当院からも記事が出ておりますので、ご参照ください。
◆腸内環境を整えて免疫力をアップさせる食事の基礎知識
<ヒスタミンの放出を抑える「ビタミンC」>
効果:抗酸化作用があり、ヒスタミンの放出を抑える
食品:レモン、オレンジ、パプリカなど
ビタミンCはヒスタミンの過剰な放出を抑える働きがあります。
そのため、花粉症の症状を軽減する効果が期待できます。ビタミンCを効率良く摂取する方法として、毎日フルーツや野菜を摂ることをおすすめしています。
<免疫機能を調整する「ビタミンD」>
効果:免疫機能のバランスを整える。
食品:卵、キノコ、魚類(鮭・まぐろ等)など
ビタミンDは免疫調整に重要な栄養素で、アレルギー症状を緩和してくれる働きがあります。
<抗アレルギー作用のある「ポリフェノール」>
効果:ヒスタミンの働きを抑える。
食品例:緑茶、リンゴなど
ポリフェノールには抗酸化作用があり、花粉症の症状を抑える効果あります。
特に緑茶のカテキンやリンゴは、ヒスタミンの働きを抑える作用があるため花粉症の時期には意識的に摂取していきましょう。
3. 栄養士が提案する花粉症対策レシピ

花粉症の方におすすめのレシピをご紹介します。
毎日のお料理にプラスできる一品となっておりますので、ぜひ作ってみてください。
『3分で作れる!切り干し大根のゆかり和え』
【材料(2人分)】
・切り干し大根(乾燥) … 25g(両手の手のひら程)
・りんご酢 … 大さじ2
・ゆかり … 小さじ1
【作り方】
- 切り干し大根を水で戻す(約20分)
- 切り干し大根を食べやすい大きさに切る
- リンゴ酢・ゆかりを切り干し大根と合わせ、ピンク色になるまで混ぜる
腸内環境が改善されるとアレルギー物質が体の中に入るのをブロックしてくれます。
今回使用しているリンゴ酢にはポリフェノールが含まれており、花粉症やアレルギーの改善が期待できるといわれていますよ。
免疫アップ!『納豆と鮭の和風炊き込みご飯』
【材料】(2~3人分)
・米 … 2合
・生鮭(または焼き鮭)… 1切れ
・納豆 … 1パック(※後入れ)
・しめじ … 1/2パック
・舞茸 … 1/2パック
・大葉 … 5枚(千切り)
・醤油 … 大さじ1
・みりん … 大さじ1
・だし汁 … 400ml(または水+和風だし小さじ1)
【作り方】
- 米を洗い、30分ほど浸水させる。
- しめじ・舞茸は石づきを取ってほぐし、鮭は骨を取り除く(生の場合は軽く焼いておく)。
- 炊飯器に米・だし汁・醤油・みりんを入れ、鮭・きのこをのせて炊飯する。
- 炊き上がったら鮭をほぐし、納豆を加えてさっくり混ぜる。
- 大葉を散らして完成!
仕上げにえごま油を加えると、さらに花粉症対策になりますよ。
4. 当院で行っている栄養指導について

当院では管理栄養士が22人在籍しており、月間栄養指導数530件の実績があります。
多くの栄養指導を行っている自信があるからこそ、花粉症を改善したい方にしっかりとヒアリングを行い、一人一人に合わせた栄養指導を実施しております。
お薬だけでなく、食事の面から管理栄養士がサポートすることで、問題を見つけ解決し、多くの患者様に喜んでいただいております。
毎年辛い花粉症だからこそ、食生活を見直すことで少しでも症状を緩和し過ごしやすい毎日にしましょう。
5.まとめ
花粉症対策には、日頃の食事が重要な役割を果たします。
抗炎症作用のあるEPA・DHA、腸内環境を整える乳酸菌・乳酸菌生産物質、ヒスタミンの放出を抑えるビタミンCなど、バランスよく摂取することが大切です。
花粉症に悩んでいる方は、ぜひ今日から食生活を見直し、症状緩和を目指してみてください!